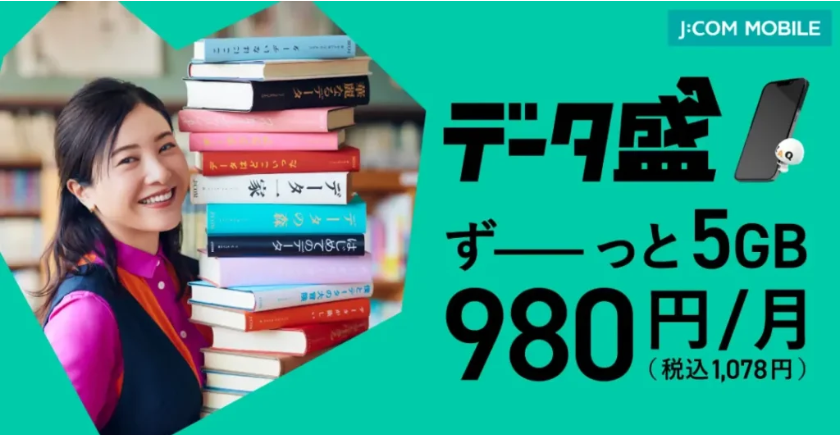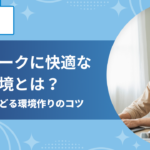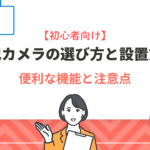MENU
最近では、小学生でもスマホを持つ家庭が増えてきました。子ども用スマホは、安全面や利便性が高い一方で、犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、何歳からスマホを持たせるべきか迷っている方向けに、子どもにスマホを持たせるメリットとデメリット、スマホを選ぶ際のポイントについて解説します。ぜひ最後までお読みください。
なお、比較的安価で利用できて、子どもが安心して使えるサポートが満載のスマホを探している方には「J:COM MOBILE」もおすすめです。
興味がある方は、以下のサイトより詳細をご確認ください。
子どもにスマホを持たせる平均年齢
子どもがスマホを持ち始める平均年齢は、10〜12歳の小学校高学年です。
令和6年のこども家庭庁の「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、年齢別のスマートフォンの専用率は以下です。
小学生(10歳以上):70.4%
中学生:93.0%
高校生:99.3%
中学生になるとほとんどの子どもが自分専用のスマホを持っていることに。
塾や習い事の連絡手段として持たせるケースや、友人とのLINEグループ参加を目的に持つケースが多いようです。
ただし、このデータはあくまで統計的な数値で、家庭や地域、学校の方針によって持たせる時期が異なる点は理解しておきましょう。
スマホを持つ子どもが増えている理由
スマホを持つ子どもが増えている背景には、いくつかの理由があります。
まず、防犯対策として位置情報の共有や緊急時の連絡手段として活用されるケースが増加しています。
また、SNSやグループチャットの普及により「スマホがないと仲間外れになるのでは?」という親の不安や子どもの希望から、スマホを持たせる家庭も多いようです。
さらに、ゲームや動画などの娯楽、学習や情報収集ツールとしても重要な役割を果たしています。
最近では、子ども向けの格安スマホや保護者による利用制限機能(ペアレンタルコントロール機能)も充実しています。
家庭の経済的・心理的な負担が軽減されたことも、普及を後押ししているようです。
子どもにスマホを持たせるメリット
子どもにスマホを持たせた場合、外出先での連絡が取りやすくなり、防犯対策としても役立ちます。
また、位置情報の共有や緊急時の連絡手段としても便利です。ここでは、子どもにスマホを持たせる主なメリットについて詳しく解説します。
親子間の連絡がスムーズになる
子どもにスマホを持たせるご家庭では、親子間の連絡が格段にスムーズになります。
塾や習い事の送迎に関する連絡が手軽にできるうえ、急な予定変更や遅れなどもすぐに伝えられる点も便利です。
また、子ども側からも自分の位置情報を報告しやすくなるため、子どもが出かけている際の親の安心感も高まります。
子どもとの連絡が取りづらくて困った経験がある家庭は、一度子ども用スマホを検討しても良いでしょう。
防犯や安全対策になる
多くの子ども用スマホには、GPS機能が付いています。GPS機能を活用すれば、子どもの現在地をリアルタイムで確認でき、トラブルの防止につながります。
さらに、防犯アプリをインストールしておけば、万が一の際にSOSを発信することも可能です。
また、親のスマホに位置情報を自動で通知するサービスもあり、学校からの帰宅時間や移動ルートを把握しやすくなります。
子どもを遠くから見守れる安心感も、子ども用スマホを持たせるメリットのひとつです。
学習や情報収集に役立つ
スマホは、子どもの学習や情報収集にも大きく役立ちます。辞書アプリや学習アプリを使えば、家庭での自習をサポートすることも可能です。
さらに、子ども向けの知育アプリやプログラミング教材も充実しており、楽しく学べる環境にアクセスしやすいのも特徴です。
子どもが気軽にニュースや学習動画に触れることで、世界への関心も広がり、新たな学びの機会にもつながりやすいでしょう。
小学生にスマホを持たせるデメリット
子どものスマホ所持は、コミュニケーションや学習の利便性が高まる一方で、ネットいじめや有害サイトなどのトラブルに巻き込まれるリスクも高まります。
また、端末代や通信費などが継続的に発生するため、家計への負担を考えることも大切です。
使用目的やルールを明確にし、慎重に検討しましょう。
スマホに依存してしまうリスクがある
スマホを持ったことをきっかけにゲームやSNSに長時間熱中してしまう子どももいます。
学業に悪影響を及ぼすだけでなく、生活リズムが乱れて心身の成長に悪影響を及ぼすことも。
親の目が届かない時間帯に使う場合、依存症の兆候に気づきにくくなるほか、使用時間がさらに増えることもあるでしょう。
常に親が使用状況を確認できる環境や、使用時間に関するルールを決めることが重要です。
犯罪やトラブルに巻き込まれる可能性もある
子どもがスマホを使う際には、SNSを通じて犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクに注意が必要です。
さらに、詐欺サイトや架空請求などの金銭トラブル、個人情報の無断公開によるトラブルも発生しています。
また、ネットいじめや誹謗中傷によって精神的に傷つくケースにも注意しなければいけません。子どもがスマホを使う前には、正しい使い方を指導しておきましょう。
費用がかかる
子どもにスマホを持たせた場合、端末代や毎月の通信費が発生し、家計の負担が増えます。さらに、故障時の修理費やプラン変更による長期的なコスト増も考慮しておきましょう。
子ども用スマホの費用負担を抑えたい方には、YCVの「J:COM MOBILE」など、安心サポート付きの格安スマホがおすすめです。
子どもにスマホを持たせるときのポイント
子どもにスマホを持たせることで利便性が向上しますが、トラブルに巻き込まれるリスクも高まります。SNS上のいじめや詐欺、不適切な情報への接触など、事前に注意すべきポイントを確認しておくことが大切です。
スマホを使う目的を明確に決めておき、安心して利用できる端末やサービスを選びましょう。
スマホを持たせる目的を明確にする
子どもにスマホを持たせる際には、まず「何のために持たせるのか」を明確にし、家庭内で共通認識を持つことが大切です。
利用目的をはっきりさせることで、機能制限やアプリの選定も的確に行えます。
子どもにもゲームや娯楽だけの道具ではないことを伝え、使用目的を理解させることが重要です。
家庭内のルールを決める
初めて子どもにスマホを持たせる際には、家庭内で明確なルールを決めておくことが重要です。
利用時間や場所、どんなシーンで使ってよいかを事前に話し合い、アプリのインストールやSNSの利用は必ず保護者が確認しましょう。
また、使用履歴や利用状況を定期的にチェックできる仕組みを整えると安心です。
さらに、家族全体でスマホの使い方を定期的に見直す機会を設けることで、ルールを守って使えるようになります。
安心できる端末やサービスを選ぶ
子どもにスマホを持たせる際には、安全機能が充実した端末やサービスを選ぶことが大切です。
ペアレンタルコントロール機能が搭載されている機種であれば、アクセス制限や利用時間の管理が可能です。
また、月額料金や契約内容も事前に確認し、家計に負担をかけない範囲のサービスを選びましょう。
まとめ|親子で安心できるスマホ選びを始めましょう
子ども用スマホは、子どもとの連絡手段や安全確保、学習のサポートなど多くのメリットがあります。
一方で、スマホ依存や犯罪などのトラブルに巻き込まれるリスク、費用面でのデメリットには注意しなければいけません。
スマホによるリスクを避けるためには、家庭内でルールを設け、ペアレンタルコントロール機能の活用など、親子で安心して使える環境づくりをすることが大切です。
コストを抑えつつ安心のサービスを利用できるスマホをお探しの方は、格安で手厚いサポートを受けられるサービスを選びましょう。
安心して使える料金プランやサポート体制が整っているスマホをお探しの方には、YCVの「J:COM MOBILE」もおすすめです。月々税込 1,078円から利用できるプランも!
興味がある方はぜひチェックしてみてください。